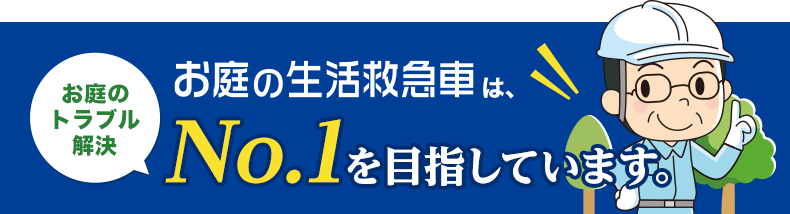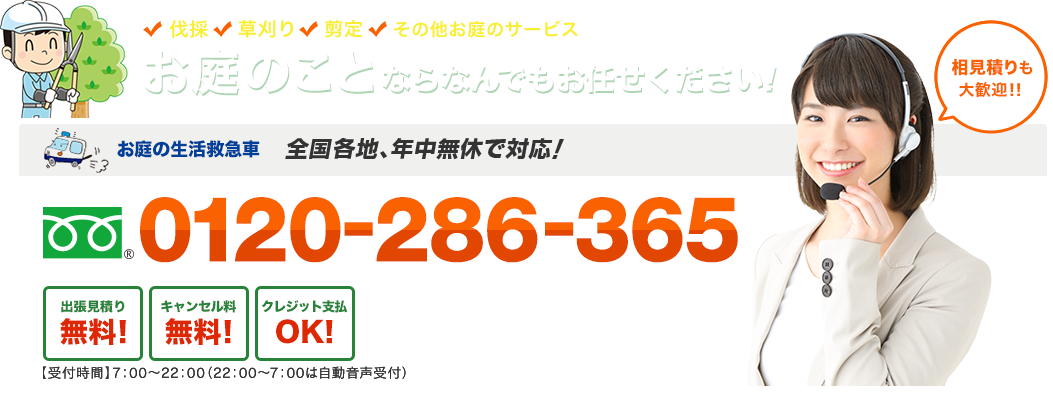目次
落葉樹の剪定は必ず冬場に行う

そもそも庭木を剪定するのはなぜなのでしょうか。もともと雑木林に生えていた樹種は、過酷な環境の中でも育っていくほど強い生物です。庭木においても、日当たりや風通しが良いなどの生育条件が揃えば、驚くほどのスピードで成長してしまいます。かといって、育ちすぎたからと当てずっぽうで切ったりすると、切り口から無数の小枝が吹き出し、本来の樹形が損なわれてしまいます。
落葉樹の剪定を冬場にやっておく理由は、第一に活動期に剪定してしまうと、樹木の生長にダメージを与えてしまうからです。樹木も、四季とともに生育サイクルを持っています。剪定によるダメージを最小限にできるのが、休眠期である冬場なのです。ただ、休眠期だからといって、やみくもに剪定を行ってはいけません。寒さが厳しいと、剪定した切り口が枯れてしまうこともあります。その場合は、休眠期ぎりぎりの3月に行うこともあります。ご自身で判断できないようなときは、専門業者に相談してみましょう。
また、冬場の方が樹木の日当たりがわかりやすいという理由もあります。太陽が高い夏場だと、どの樹木にも日が当っており、区別がつきません。しかし、太陽の位置が低くなる冬場であれば、どの木に日が当たり、どの木に日が当っていないのかがわかります。そうすれば、どの樹木にも土にも日が当たるように、庭木の剪定ができるのです。冬場の落葉樹には葉っぱがありませんので、枝の込み具合も目で見てわかります。剪定作業もはかどるはずです。
落葉高木のウメ、サルスベリ、ハナミズキの剪定方法
落葉樹には、高木と低木の2種類があります。落葉高木は、ウメやサルスベリ、ハナミズキなどが、その代表です。 ウメを剪定する場合、もっとも重要なのは花芽文化期後に剪定することです。ウメは、7月ごろに花芽がつき、8月いっぱいで花芽が決まります。早い時期に剪定してしまうと、葉芽に栄養を取られて花芽がつきにくくなってしまいます。とがっているのが葉芽で、ふっくら丸いのが花芽ですが、初心者には見分けるのが難しいので、つぼみがはっきりする11月~2月にかけて剪定するのが良いでしょう。「桜切るバカ、梅切らぬバカ」といわれるように、ウメの場合、伸びすぎた徒長枝を剪定する必要があります。徒長枝には花芽がほとんどつかず、放っておくと養分や水分をもっていかれて他の小枝にも悪影響が及びます。徒長枝は切り残すと、そこから新たに勢いのある徒長枝が生えてきますので、枝元からばっさり切ります。また、幹から直線的に伸びる太い枝も、樹勢が強すぎるので剪定してしまいましょう。
サルスベリは、剪定を行わないと開花の量にばらつきが出てしまい、悪くすると隔年開花になる恐れもありますので、剪定を怠らないことが鉄則です。夏に開花するサルスベリですが、花後すぐに剪定すると、切り口から徒長枝になりやすい土用枝が伸びてしまいます。そこから花芽をつける枝は生えてきますが、花が小さくなってしまいますので、12月に入ってから剪定します。しかし、サルスベリは毎年同じ箇所ばかりを切ってしまうと、枝の一部が膨らむコブという状態になります。好き嫌いはありますが、あまりに大きくなりすぎると見苦しいので、根元を残す箇所を毎年変えることでコブを防ぐようにします。また、あまり強い剪定はせずに、徒長枝は際から切り、古い枝や乱れた枝だけを選んで、全体の1/2ほどの枝を剪定するのが良いでしょう。
ハナミズキは枝が横に張って伸びるので、張り出してしまった枝や徒長枝を、付け根から全体の2/5ほど切り落とします。また、落葉期になると葉芽ばかりの枝が目立ってきます。この枝を放置しておくと葉ばかりが多くなってしまいますので、必ず剪定するようにします。
落葉低木のモクレン、フヨウ、ライラックの剪定方法
落葉低木のモクレンは樹高が高くなりがちなので、基本的に上への生長を抑制する剪定を行います。そのため、庭に調和する位置で樹芯を切って頭をとめます。植えるときに、根の下に石などを置いておくと根が横に広がり、枝も横に広がります。剪定の際に、下向きの枝を残すことで花をたくさんつけることができますが、木の勢いはなくなります。樹勢がなくなるとヤゴ(根元から立ちあがる枝)が発生し、花が咲かなくなってしまいますので、剪定するときには下向きの枝ばかりにしないよう注意が必要です。また、モクレンは枝が直線的に伸びるので、枝の途中で切るとゴツゴツした枝ぶりになってしまいます。必ず付け根から切り落とします。 フヨウは樹勢が強いので、刈り込んでも枯れることはありません。しかし、冬を迎えると地上部は枯れてきます。そのまま放置すると、翌年の花が小さくなってしまうので、落葉が終わってから地上15~20センチの高さで刈り取ります。そして、乾燥を防ぐために、その上に落ち葉や腐葉土を厚く敷いてあげましょう。また、込み合った枝が出ていたら、古いものを付け根から切り落とします。冬場の剪定では、全体の1/4程度の枝を間引くように剪定すると良いでしょう。
ライラックは、日の差す方向に枝を伸ばし、放っておくと花の位置が上がってしまいます。そのため、枝が横ぶりになるように剪定します。頭頂部付近の立ちあがった枝や、樹冠内部で込み合った枝は、付け根から切り落とします。ただ、太い枝を一度に切ると枯れてしまいますので、あまり古くならないうちに早めに切るよう心がけてください。コンパクトにしたい場合は、花後すぐに古くて太い枝を付け根で切り、強く伸びた枝を中心に全体の1/4くらいをめどに切り取ります。
■まとめ

剪定のお役立ち情報
-
お手入れが少なくて済む庭木の人気種
庭木を植えると庭が賑やかになるだけでなく、通りから家の中が丸見えにならないように目隠しの役割を果たしてくれたり、雨風から家を守ってくれたりと、さまざまなメリットがあります。とはいえ、庭木はお手入れが大変だと思っている人もいるのではないでしょうか。庭木のなかには、お手入れが少なくて済む種類もあるのです。この記事では、初心者でも育てやすく人気のある樹種について紹介します。
-
庭の落ち葉は放置してはいけない?秋の庭の手入れ
秋は落ち葉や枯れ葉が多くなるため、お庭の手入れをまめに行う必要があるタイミングです。しかし、自分でお庭の手入れをしようとすると時間も体力も必要です。とはいえ、たまった落ち葉を放置しておくわけにもいきません。この記事では、秋に行うお庭の手入れについて解説していきます。
-
庭に関するご近所トラブルに要注意!ありがちなトラブルと回避方法について
ご近所との良好な関係を維持するためにも、トラブルはできるだけ避けたいものです。しかし、トラブルを起こさないようにするには、どのような行為が迷惑にあたるのかを事前に知っておく必要があります。特に庭付きの家や、ガーデニングが好きな家庭には庭を巡るトラブルがつきものです。そこで、庭に関するよくあるトラブルや、トラブルを回避するための方法を紹介します。
-
初心者必見!剪定はなぜ必要?どの枝を切ればいい?剪定の基本
庭の樹木が伸びてきて、見た目が悪くなってしまったときに行うのが剪定です。剪定には必要な枝のみを残す技術と、適切なタイミングが求められます。事前に知識をつけず適当に枝を切ってしまうのは、「花が咲かない」「周辺の木々も枯れる」というトラブルが起こる原因です。この記事では、剪定の方法や切るべき枝の見分け方を紹介します。
-
剪定をプロに頼むとかかる費用はどれくらい?剪定の相場をご紹介
せっかく立派な庭を持っていても、それを美しい状態のまま維持するのは大変です。放置をしていると、手入れをしていない髪と同じですぐにぼさぼさになってしまいます。定期的に剪定をしたいところですが、素人ひとりでそれを行うのは大変です。一方、プロに依頼すると料金が気がかりかもしれません。そこで、剪定を業者に依頼した場合の費用の相場とその費用をなるべく抑える方法について解説をしていきます。
私たちお庭の生活救急車は、お客様に「頼んでよかった」と言って頂けるようなサービスの向上を目指しております。そのためにきちんとお客様のお話を伺い、ひとつひとつのトラブルをしっかり調べ、作業後のアドバイスもさせて頂いております。また接客技術にもこだわっており、講師を招いて接客サービスの徹底教育行い、親切かつ丁寧なサービス提供に努めています。これからもスタッフ一同、お客様を助けたいという思いをもとに対応してまいります。